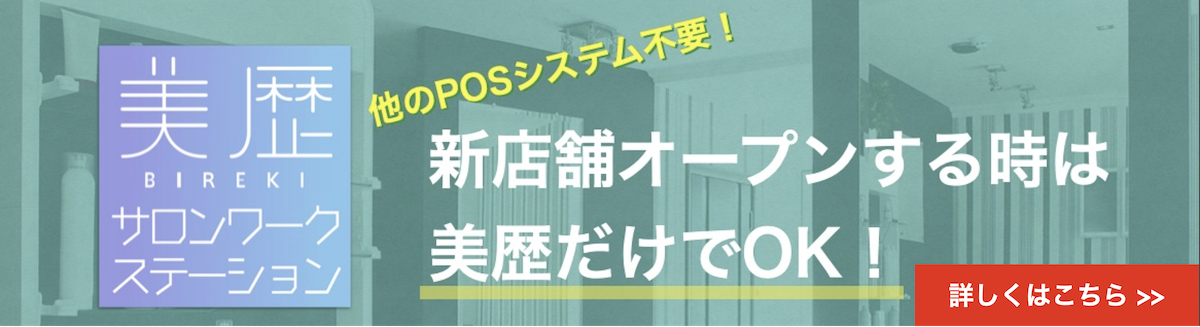|キャリアは19歳のフリーランスライターから
私は19歳の大学生から、
フリーランスのライターとして、
仕事をすることとなった。
そのきっかけはまたの機会に、
話すことがあれば。
|タブーがまだたくさんあった時代
その駆け出しライターが20歳そこそこのとき、
某総合出版社の某情報誌にて、
『新宿ラブホ特集』をすることとなった。
今となっては、
ラブホはごくごく普通名詞だが、
”ラブホテル”というワードが、
総合出版社では使いにくい時代。
というか、
総合出版社の一般誌で
”ラブホ”
なんてワードは御法度な時代だった。
|青年の既成概念を覆したひとりの女性
にもかかわらず、
当時の女性編集長は、
「若い人が読む雑誌なんだから、
そのくらい当たり前でしょ!」
と言い放った。
この言葉は新鮮だった。
そして輝いて聞こえた。
時代を切り開くときには、
少なからず軋轢ってものが生まれる。
これは表現者だけでなく、
ビジネスにおいても技術者においても、
同じなのではないだろうか。
まさに彼女はジャンヌ・ダルク。
|駆け出しに訪れた大きなチャンス
その彼女が私を指差して、
「石渡くん、担当しなさい」
そう、まだ駆け出しの俺を、
編集者として仕事なんてできない俺を、
小僧の俺を抜擢してくれるのか。
この人は、先鋭的なだけでなく、
先見の明もあるのではないか!
こうなったらカミカゼ特攻隊よろしく、
戦陣を争う戦国時代の若武者よろしく、
これまでにない企画を作ってみせますよ、
と、おだてたなんちゃらは木に登ったのだった。
——あとから知るのだが、
編集長は、
「若いんだから、ラブホをたくさん使っているだろう」
という理由で、部内でもっとも若い私を指名しただけだった。
そりゃそうだ、まだたいした仕事もしていない。
取材もそこそこだし、原稿は直しばっかりの、
よちよち歩きの赤ん坊。
登った木がイバラだらけの針葉樹だってことにも気づかないで。——
|独り立ちへの大きな挑戦が始まる
そんな現実のことはつゆ知らず、
意気揚々と取材の下準備を始める。
パソコンなんてなかった当時。
調べるのは”足”しかない。
昭文社の地図、マップルを引っ張りだして、
ラブホの位置を確認することからはじめた。
「この企画で俺は独り立ちできる」と、
”独り勃ち”では戦えないラブホを調べ始める。
かくして、自称・若手注目株編集者の、
「初めてのおつかい」
ならぬ、
「初めての勘違い」
がはじまるのだった。
↓最新の電子カルテはこちら!↓
美歴の機能について!